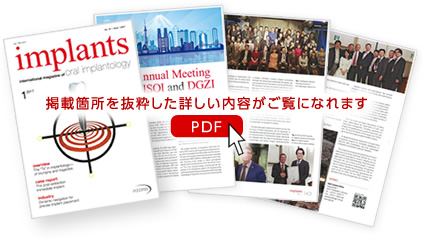冬の寒さが本格化する中、2024年12月7日、認定試験が実施され、翌8日にはAnnualMeeting 2024「インプラント長期保存に必要なハードウェア/ソフトウェア」がベルサール羽田空港で開催されました。当日は晴天で、冬の訪れを感じさせる冷え込みの中、多くの参加者が会場を訪れ、企業展示も賑わいを見せていました。
プログラムの最初を飾ったのは、ドイツからお招きしたACHIM VON BOMHARD先生です。垂直的・水平的オーギュメンテーションを活用した咬合の回復や、AI・デジタル技術を用いた口元の改善に関するご講演をいただきました。続いて、菅野太郎先生(東北大学大学院歯学研究科教授)が登壇し、話題のブルーラジカルP-01とペリミルについて解説してくださいました。特に、ブルーラジカルP-01の優れた性能だけでなく、患者さん自身によるプラークコントロールが治療の成功において重要な要素であるとの指摘が印象的でした。この点は、すべての歯科治療に通じる基本として再認識させられる内容でした。
昼食時には、2019年以来となるランチビュッフェが開催され、参加者は企業展示を見学しながら食事を楽しみました。コロナ禍で一時中断されていた企業と会員との交流が再び活発化したことを実感しました。
午後のセッションでは、佐藤隆太先生(SRデンタルクリニック)が「骨造成の意義を再考する」と題して講演されました。症例のリカバリーを交えながら、適材適所での骨造成の重要性について語られる一方で、無理に骨造成を行わずナローやショートインプラントを用いる選択肢が患者と術者双方に利益をもたらす可能性について問いかけられました。深い洞察に満ちた講演でした。
歯科衛生士部門では、山口千緒里先生(ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター)が登壇され、インプラントのメンテナンス方法や、高齢化社会における訪問診療の必要性と意義について詳しく解説されました。実践的な内容で、多くの学びを得る機会となりました。
最後に登壇されたのは、夏堀礼二先生(夏堀デンタルクリニック)です。先生は長期症例をもとに、可撤式と固定式の上部構造の有意差や、インプラント体との接合様式の違いについて詳細に解説され、参加者にとって大会の締めくくりにふさわしい内容となりました。
本大会が無事に成功を収めたのは、ご参加いただいた先生方、スタッフの皆様、そして出展いただいた企業の皆様のおかげです。心より深く感謝申し上げます。今後も、より良い学びの場を提供できるよう邁進してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
国際口腔インプラント学会
会長 吉岡 慎哉